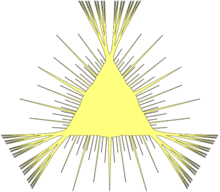数学 において掛谷集合 (かけやしゅうごう、英 : Kakeya set )もしくはベシコビッチ集合 (英 : Besicovitch set )とは、ユークリッド空間 において、全ての方向に単位線分 を持つ点の集合のことである。名称は掛谷宗一 およびアブラム・ベシコヴィッチ (英語版 )
平面において単位線分を連続的な移動により180度回転させて、線分を元の位置に向きを逆転させて戻すことができる点の集合を掛谷針集合と呼ぶ。
「ペロンツリーの成長」: 小さな測度の掛谷集合を構築する方法。ここでは、三角形を分割し、重なり合わせる二つの方法が示されている。最初は二つの三角形を使う方法で、次は八つの三角形を使う方法である。この方法は、元の三角形を
2
n
{\displaystyle 2^{n}}
[ 1] ベシコビッチ は、単位長の針が回転できるような領域
D
{\displaystyle D}
ε
>
0
{\displaystyle \varepsilon >0}
ε
{\displaystyle \varepsilon }
[ 2] ベシコビッチ集合 」と呼ばれている。ベシコビッチが任意に小さい 測度 を持つこのような集合を示したのは1919年のことであった。この問題はそれ以前から解析学者によって考えられていた可能性がある。
ベシコビッチ集合を構築する一つの方法(対応する図を参照)は、オスカー・ペロン にちなんで「ペロンツリー」と呼ばれ、ベシコビッチの元の構築法を簡略化することができた[ 3] [ 1]
最初に観察すべきことは、針が直線上をどれだけ遠くまで動くことができるかということである。これは、針が幅ゼロの線分だからである。次のトリックはパール によって知られる「パール結合 」[ 4]
r
{\displaystyle r}
1
/
r
{\displaystyle 1/r}
構築は、高さ1の任意の三角形から始まり、針が容易に掃くことができる上部にかなりの角度がある。この三角形に対して多くの操作を行い、その面積を小さくしながら針が掃くことができる方向を同じに保つことが目標となる。 まず、三角形を二つに分け、それらの基部が重なり合い、全体の面積を最小限に抑えるように変形する。針は、最初の三角形によって与えられた方向を掃き出し、二つ目の三角形にジャンプして、その後二つ目の三角形によって与えられた方向を掃き出すことで、同じ方向を掃き出すことができる。針は、「N」技術を使用して三角形をジャンプすることができる。元の三角形が切られた二つの線は平行であることからこれが可能となる。
三角形を 2n n 回繰り返し、一つの形状だけになるまで続ける。再び、針はそれぞれの 2n
残るのは、最終形状の面積を計算することである。証明は難しいので省略する。代わりに、数がどのようになるかを説明する。 図を見れば、2n i 回の統合操作から作成された各形状の面積が A i A i 2
A i+1 A i
A 0 -n
A n n -n 1/n になる。 n が増加するにつれて、この面積はゼロに収束する。 ベシコビッチ集合は、正三角形から作成されたペロンツリーの六つの回転を組み合わせることによって作成できる。 平行四辺形を使用しても同様の構築が可能である。
他にも「成長」法以外で測度ゼロのベシコビッチ集合を構築する方法がある。 例えば、カハーヌ は、カントール集合 を用いて二次元平面における測度ゼロのベシコビッチ集合を構築している[ 5]
ペロンツリーから構築された掛谷針集合。 1941年、H. J. ヴァン・アルフェン[ 6] I. J. ショーンバーグ は独立に、面積が
π
24
(
5
−
2
2
)
{\displaystyle {\tfrac {\pi }{24}}(5-2{\sqrt {2}})}
ブルーム・ショーンバーグ数 」と呼ばれている。ショーンバーグは、この数が単連結掛谷針集合の面積の下限であると予想した。しかし、1971年には F. カニンガム[ 7]
任意に小さい正の測度を持つ掛谷針集合と測度ゼロのベシコビッチ集合は存在するが、測度ゼロの掛谷針集合は存在しない。
任意の正の数よりも小さい面積の掛谷針集合が存在する。[ 8]
最小の凸 掛谷針集合は一辺
2
/
3
{\displaystyle {2/{\sqrt {3}}}}
[ 9]
半径 1 の円の内部で任意の正の実数 ε に対し
π
108
{\displaystyle {\tfrac {\pi }{108}}}
単連結 掛谷針集合が存在する。[ 10]
これらのベシコビッチ集合がどれほど小さくなり得るかという同様の問題が高次元で提起され、「掛谷予想」として知られるいくつかの予想が生まれ、幾何測度論 と呼ばれる数学の分野の発端となった。特に、測度ゼロのベシコビッチ集合が存在する場合、これらはそれらが存在する空間の次元よりも小さい次元の s 次元 ハウスドルフ測度 がゼロである可能性があるのか?という問題が生じる。この問題は次の予想を導く:
掛谷集合予想 : R n ベシコビッチ集合 を、あらゆる方向に単位線分を含む集合として定義する。そのような集合は必ず ハウスドルフ次元 と ミンコフスキー次元 が n に等しいか?これは n = 1 および 2 の場合に真であることが知られているが、高次元の場合には部分的な結果しか知られていない。
この問題に対する現代的なアプローチの一つは、次のように構成される特定のタイプの 最大関数 を考慮することである:S n −1R n
T
e
δ
(
a
)
{\displaystyle T_{e}^{\delta }(a)}
a ∈ R n e ∈ S n −1局所可積分 関数 f に対して、f の 掛谷最大関数 を次のように定義する。
f
∗
δ
(
e
)
=
sup
a
∈
R
n
1
m
(
T
e
δ
(
a
)
)
∫
T
e
δ
(
a
)
|
f
(
y
)
|
d
m
(
y
)
{\displaystyle f_{*}^{\delta }(e)=\sup _{a\in \mathbf {R} ^{n}}{\frac {1}{m(T_{e}^{\delta }(a))}}\int _{T_{e}^{\delta }(a)}|f(y)|dm(y)}
ここで m は n 次元 ルベーグ測度 を表す。
f
∗
δ
{\displaystyle f_{*}^{\delta }}
S n −1e に対して定義されている。
次に、これらの関数に対して次の予想がある。これが真であれば、より高次元の掛谷集合予想を示唆する:
掛谷最大関数予想 : 任意の ε > 0 に対して、任意の関数 f とすべての δ > 0 に対して次のような定数 Cε > 0 が存在する:
‖
f
∗
δ
‖
L
n
(
S
n
−
1
)
⩽
C
ϵ
δ
−
ϵ
‖
f
‖
L
n
(
R
n
)
.
{\displaystyle \left\|f_{*}^{\delta }\right\|_{L^{n}(\mathbf {S} ^{n-1})}\leqslant C_{\epsilon }\delta ^{-\epsilon }\|f\|_{L^{n}(\mathbf {R} ^{n})}.}
掛谷予想を証明するためのいくつかの結果は次の通りである:
掛谷予想は n = 1 (自明に)および n = 2(Davies[ 11]
任意の n 次元空間において、Wolff[ 12] n +2)/2 であることを示した。
2002年、Katz と Tao [ 13]
(
2
−
2
)
(
n
−
4
)
+
3
{\displaystyle (2-{\sqrt {2}})(n-4)+3}
n > 4 に対してより良くなった。
2000年、Katz 、Łaba 、および Tao[ 14] ミンコフスキー次元 が 5/2 よりも厳密に大きいことを証明した。
2000年、Jean Bourgain は掛谷問題を 算術組合せ論 [ 15] [ 16] 調和解析 および 加法的数論 を含む問題に発展させた。
2017年、Katz と Zahl[ 17] ハウスドルフ次元 の下限を
5
/
2
+
ϵ
{\displaystyle 5/2+\epsilon }
ϵ
>
0
{\displaystyle \epsilon >0}
やや驚くべきことに、これらの予想は、特に調和解析 における他のいくつかの問題に関連していることが示されている。例えば、1971年にチャールズ・フェッファーマン は、ベシコビッチ集合の構成を利用して、次のことを示した。次元が1を超える場合、原点を中心とした半径が無限大に向かう球体上で取られるトランケート・フーリエ積分は、L p p ≠ 2の場合)で収束しないことがある(これは、一次元の場合においてそのようなトランケート積分が収束するのとは対照的である)。[ 18]
掛谷問題の類似として、直線以外のより一般的な形状を含む集合を考えることがある。例えば、円を考える。
1997年[ 19] [ 20] 半径ゼロの周りの球を含む集合が存在するという予想が立てられた。エリアス・スタイン の結果[ 21] n ≥ 3のとき、すべてのそのような集合は正の測度を持たなければならないことを証明した。また、マーストランド[ 22] n=2 の場合でも同様のことを証明した。
掛谷予想の一般化として、すべての方向における直線のセグメントの代わりに、k 次元部分空間の部分を含む集合を考える。(n , k )-ベシコビッチ集合 K を、レベーグ測度がゼロであるR n B を原点を中心とする単位球とし、任意のk 次元部分空間P に対して、P ∩ B に対してx ∈ R n P ∩ B ) + x ⊆ K となるようにする。したがって、(n , 1)-ベシコビッチ集合は、先に述べた標準的なベシコビッチ集合である。
(n , k )-ベシコビッチ予想: k > 1の場合、(n , k )-ベシコビッチ集合は存在しない。1979年、マーストランド[ 23] ケネス・ファルコナー [ 24] k > n の場合、(n , k )-ベシコビッチ集合が存在しないことを証明した。これまでの最良の境界はブルゲイン[ 25] k −1k > n の場合には、そのような集合は存在しないことが証明されている。
1999年、ウルフは掛谷問題の有限体 に関する類似問題を提起し、この予想を解決するための技法がユークリッドの場合にも応用できることを期待した。
有限体掛谷予想 : F を有限体とし、K ⊆ F n を掛谷集合とする。すなわち、任意のベクトルy ∈ F n K が直線{x + ty : t ∈ F }を含むようにするためのx ∈ F n K は少なくともcn |F |n cn >0はn のみに依存する定数である。ゼエブ・ディヴィール は2008年にこの予想を証明した。彼は、cn = 1/n !のときにこの命題が成り立つことを示した。[ 26] [ 27] n 変数の任意の次数が|F |未満の多項式が掛谷集合上でゼロになる場合、それは恒等的にゼロである必要があることを示した。一方、n 変数の次数が|F |未満の多項式は次元が
(
|
F
|
+
n
−
1
n
)
≥
|
F
|
n
n
!
.
{\displaystyle {|\mathbf {F} |+n-1 \choose n}\geq {\frac {|\mathbf {F} |^{n}}{n!}}.}
となるベクトル空間を形成する。したがって、与えられた集合がこの数未満の点を持つ場合、次数が|F |未満の非自明な多項式が少なくとも1つ存在することになる。これら2つの観察を組み合わせることで、掛谷集合は少なくとも|F |n n !の点を持たなければならないことが示される。
この技法が元の掛谷予想を証明するために拡張されるかどうかは不明だが、この証明は本質的に代数的な反例がありそうにないことから、元の予想の信憑性を高めている。ディヴィールは、有限体の掛谷問題に関する進展とそのランダムネス抽出器 との関係に関する調査記事を執筆した。[ 28]
半径 0.5 の円板
s
≈
0.78539
{\displaystyle s\approx 0.78539}
幅 1 のルーローの三角形
s
≈
0.70477
{\displaystyle s\approx 0.70477}
一辺
2
/
3
{\displaystyle {2/{\sqrt {3}}}}
s
≈
0.57735
{\displaystyle s\approx 0.57735}
半径 3 / 4 の円に内接するデルトイド
s
≈
0.39270
{\displaystyle s\approx 0.39270}
^ a b Besicovitch, A. S. (1963年8月). “掛谷問題” . アメリカ数学月報 70 (7): 697. doi :10.2307/2312249 . ISSN 0002-9890 . http://dx.doi.org/10.2307/2312249 .
^ Besicovitch, Abram (1919). “二つの関数の積分可能性に関する問題”. J. Soc. Phys. Math. 2 : 105–123. Besicovitch, Abram (1928). “掛谷問題と類似の問題について”. 数学誌 27 : 312–320. doi :10.1007/BF01171101 . ^ Perron, O. (1928). “ベシコビッチの定理について”. 数学誌 28 : 383–386. doi :10.1007/BF01181172 . Falconer, K. J. (1985). フラクタル集合の幾何学 . ケンブリッジ大学出版局. pp. 96–99 ^ 掛谷問題 Archived 2015-07-15 at the Wayback Machine . マルクス・フルトナーによる^ Kahane, Jean-Pierre (1969). “完全線形集合に関する三つの注記”. 数学教育 15 : 185–192. ^ Alphen, H. J. (1942). “ベシコビッチの定理の拡張”. Mathematica Zutphen B 10 : 144–157. ^ Cunningham, F. (1971). “単連結集合および星状集合に対する掛谷問題” . アメリカ数学月報 (アメリカ数学月報, Vol. 78, No. 2) 78 (2): 114–129. doi :10.2307/2317619 . JSTOR 2317619 . https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Ford/Cunningham.pdf . ^ Perron, O. (1928). “Über eine Satz von Besicovitch”. Mathematische Zeitschrift 28 : 383–386. doi :10.1007/BF01181172 . Falconer, K. J. (1985). The Geometry of Fractal Sets . Cambridge University Press. pp. 96–99 ^ Pal, Julius (1920). “Ueber ein elementares variationsproblem”. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Math.-Fys. Medd. 2 : 1–35. ^ Cunningham, F. (1971). “The Kakeya problem for simply connected and for star-shaped sets” . American Mathematical Monthly (The American Mathematical Monthly, Vol. 78, No. 2) 78 (2): 114–129. doi :10.2307/2317619 . JSTOR 2317619 . http://mathdl.maa.org/images/upload_library/22/Ford/Cunningham.pdf . ^ Davies, Roy (1971). “Some remarks on the Kakeya problem”. Proc. Cambridge Philos. Soc. 69 (3): 417–421. Bibcode : 1971PCPS...69..417D . doi :10.1017/S0305004100046867 . ^ Wolff, Thomas (1995). “An improved bound for Kakeya type maximal functions”. Rev. Mat. Iberoamericana 11 : 651–674. doi :10.4171/rmi/188 . ^ Katz, Nets Hawk ; Tao, Terence (2002). “New bounds for Kakeya problems”. Journal d'Analyse Mathématique 87 : 231–263. arXiv :math/0102135 . doi :10.1007/BF02868476 . ^ Katz, Nets Hawk; Łaba, Izabella; Tao, Terence (September 2000). “An Improved Bound on the Minkowski Dimension of Besicovitch Sets in
R
3
{\displaystyle \mathbb {R} ^{3}}
The Annals of Mathematics 152 (2): 383– 446. arXiv :math/0004015 . doi :10.2307/2661389 . JSTOR 2661389 . ^ J. Bourgain, Harmonic analysis and combinatorics: How much may they contribute to each other?, Mathematics: Frontiers and Perspectives, IMU/Amer. Math. Soc., 2000, pp. 13–32.
^ Tao, Terence (March 2001). “From Rotating Needles to Stability of Waves: Emerging Connections between Combinatorics, Analysis and PDE” . Notices of the AMS 48 (3): 297–303. https://www.ams.org/notices/200103/fea-tao.pdf . ^ Katz, Nets Hawk; Zahl, Joshua (2019). “An improved bound on the Hausdorff dimension of Besicovitch sets in
R
3
{\displaystyle \mathbb {R} ^{3}}
Journal of the American Mathematical Society 32 (1): 195– 259. arXiv :1704.07210 . doi :10.1090/jams/907 . ^ Fefferman, Charles (1971). “The multiplier problem for the ball”. Annals of Mathematics 94 (2): 330–336. doi :10.2307/1970864 . JSTOR 1970864 . ^ Wolff, Thomas (1997). “A Kakeya problem for circles”. American Journal of Mathematics 119 (5): 985–1026. doi :10.1353/ajm.1997.0034 . ^ Wolff, Thomas ; Wolff, Thomas (1999). “On some variants of the Kakeya problem” . Pacific Journal of Mathematics 190 : 111–154. doi :10.2140/pjm.1999.190.111 . https://authors.library.caltech.edu/710/1/KOLpjm99.pdf . ^ Stein, Elias (1976). “Maximal functions: Spherical means” . Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 73 (7): 2174–2175. Bibcode : 1976PNAS...73.2174S . doi :10.1073/pnas.73.7.2174 . PMC 430482 . PMID 16592329 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC430482/ . ^ Marstrand, J. M. (1987). “Packing circles in the plane”. Proceedings of the London Mathematical Society 55 : 37–58. doi :10.1112/plms/s3-55.1.37 . ^ Marstrand, J. M. (1979). “Packing Planes in
R
3
{\displaystyle \mathbb {R} ^{3}}
Mathematika 26 (2): 180–183. doi :10.1112/S0025579300009748 . ^ Falconer, K. J. (1980). “Continuity properties of k-plane integrals and Besicovitch sets”. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 87 (2): 221–226. Bibcode : 1980MPCPS..87..221F . doi :10.1017/S0305004100056681 . ^ Bourgain, Jean (1997). “Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis”. Geometric and Functional Analysis 1 (2): 147–187. doi :10.1007/BF01896376 . ^ Dvir, Z. (2009). “On the size of Kakeya sets in finite fields”. Journal of the American Mathematical Society 22 (4): 1093–1097. arXiv :0803.2336 . Bibcode : 2009JAMS...22.1093D . doi :10.1090/S0894-0347-08-00607-3 . ^ テレンス・タオ (2008年3月24日). “Dvir's proof of the finite field Kakeya conjecture ”. What's New . 2008年4月8日 閲覧。^ Dvir, Zeev (2009). “From Randomness Extraction to Rotating Needles”. ACM SIGACT NewsTemplate:ECCC .